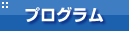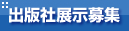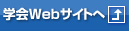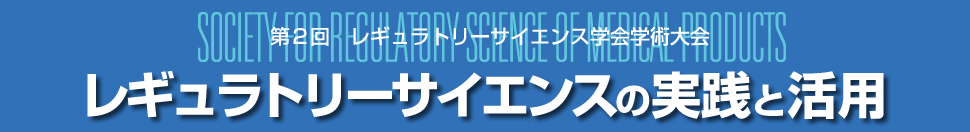
テーマ:レギュラトリーサイエンスの実践と活用
開催期間: 平成24年(2012年)9月2日(日)~9月3日(月)
大会長: 大野 泰雄 (国立医薬品食品衛生研究所 所長)
開催場所: 学術総合センター(千代田区一ツ橋2-1-2) [会場案内図]
■会長講演 12:45~13:15(会場:一橋講堂)
- 大野 泰雄 (国立医薬品食品衛生研究所 所長)
■特別講演 13:15~15:45(各45分、途中15分休憩) (会場:一橋講堂)
- 永井 良三 (自治医科大学 学長)
- 手代木 功 (日本製薬工業協会 会長)
- 加藤 尚武 (鳥取環境大学 名誉学長)
■シンポジウム
1) 国際共同開発によるNDA-有効性・安全性評価はどうあるべきか ?-
16:00~18:00 会場:一橋講堂
西田 ちとせ(日本製薬工業会)
「国際共同開発の現状と課題-日本人症例数の設定根拠とその評価の観点から-」
小宮山 靖(ファイザー)
「グローバル・データパッケージを用いた薬効評価はどうあるべきか」
宇山 佳明(医薬品医療機器総合機構)
「未定」
■シンポジウム
2) 薬物性心毒性への新たなるアプローチ
16:00~18:00 会場:特別会議室101~103
早川 智広(ソニー 先端マテリアル研究所)
「高速イメージングによる非侵襲な心筋拍動評価(仮)」
西岡 絹恵(医薬品医療機器総合機構)
「ICH-E14ガイドラインの開発・審査段階における現状と今後の展望について」
諫田 泰成(国立医薬品食品衛生研究所)
「ヒトiPS細胞を用いた心毒性評価の現状と課題」
杉山 篤(東邦大学医学部)
「薬物性心毒性:動物からヒトへのトランスレーショナルリサーチ」
■ 一般演題(口演)
11:00~ 会場:中会議室2~4、会議室101~202
■シンポジウム
3) FIH試験をわが国に根付かせるために-現状と課題-
9:30~11:30 会場:一橋講堂
小林 真一(昭和大学医学部)
「FIH試験の初回投与量設定」
熊谷 雄治(北里大学医学部)
「FIH試験の実際」
川崎 ナナ(国立医薬品食品衛生研究所)
「バイオ医薬品のFIH試験」
辻出 清和(日本製薬工業協会)
「製薬企業から見たわが国のFIH試験」
光岡 俊成(厚生労働省)
「FIH試験のレギュラトリーサイエンス」
4)ファーマコゲノミクスを医薬品開発および市販後安全対策に役立てるには -現状、課題と解決に向けて-
9:30~11:30 会場:中会議室1,2
鎌谷 直之(スタージェン)
「ファーマコゲノミクス検査の実用における統計疫学的考察」
劉 世玉(武田薬品工業)
「企業におけるPGx利用の現状と課題」
鳥谷部 貴祥(医薬品医療機器総合機構)
「PMDAでのPGxに基づく薬剤治療の普及のための取組みと課題」
山縣 然太朗(山梨大学大学院医学工学総合研究部)
「PGx研究におけるELSI(倫理的、法的、社会的諸課題)」
5) 医療現場へ還元できる科学的な製造販売後調査
9:30~11:30 会場:中会議室3,4
久保 忠道(バイエル薬品)
「企業側から見た製造販売後調査の現状と課題」
小林 巧(ヤンセンファーマ)
「JAPhMedからの課題指摘と改善提案」
堀 明子(医薬品医療機器総合機構)
「リスクマネジメントプランと PMDAの取り組み」
別府 宏圀(新横浜ソーワクリニック )
「PMS調査に関する診療現場の見方と期待」
赤座 英之(東京大学先端科学技術研究センター)
「市販後全例調査(使用成績調査)の有効利用」
6) 薬物間相互作用ガイダンスの改訂に向けて
12:45~14:45 会場:一橋講堂
杉山 雄一(理化学研究所)
「欧米の薬物間相互作用(DDI)ガイダンスの現状と科学的基盤」
泉 高司(第一三共)
「新薬開発における薬物間相互作用評価の重要性」
岸本 航(日本ベーリンガーインゲルハイム )
「薬物トランスポーター試験の現状に関するアンケート調査」
岩田 大祐(医薬品医療機器総合機構)
「承認審査における薬物相互作用の検討(審査の立場から)」
7) 医薬品・医療機器などの製造販売承認の意義とそれを改革するための政策ツール
12:45~14:45 会場:中会議室1,2
磯部 哲(慶應義塾大学法科大学院)
「法学からみた製造販売承認の位置づけ(仮)」
小塩 篤史(日本医科大学)
「経済学からみた製造販売承認の意味(仮)」
仙石 慎太郎(京都大学細胞統合システム拠点)
「イノベーションマネジメントからみた製造販売承認のあり方(仮)」
平野 景子(順天堂大学医学部)
「臨床および研究の場面からみた製造販売承認について(仮)」
8) 経済産業省・厚生労働省連携事業「次世代医療機器開発ガイドライン・評価指標作成事業」の7年間を振り返って
12:45~14:45 会場:中会議室3,4
許 俊鋭(東京大学医学部)
「人工心臓の申請にかかわるガイドラインと市販後の安全管理(仮)」
大槻 孝平(医薬品医療機器総合機構)
「植込み型補助人工心臓の承認審査概要」
小池 和央(医薬品医療機器総合機構)
佐藤 正人(東海大学医学部)
「軟骨細胞シートの事例からみたヒト幹細胞臨床研究の取り組み」
田中 直子、田崎雅子(テルモ)
「再生医療製品開発での非臨床安全性・有効性評価-ヒト(自己)指針-」
9) 希少疾病医薬品開発の現状と課題 -開発促進に向けて-
15:00~18:00 会場:一橋講堂
中村 秀文(国立成育医療研究センター)
楠 博文(独立行政法人医薬基盤研究所)
「希少疾病医薬品開発の現状と課題」
大塚 清(グラクソ・スミスクライン)
「品質に係る問題(製薬協内でのアンケート調査結果を含む)」
吉沢 昭浩(日本製薬工業会)
「規制・臨床に係る問題(製薬協内でのアンケート調査結果を含む)」
10) Radical Uncertainty とPublic Dialogue~有効性と副作用の相克を超えて
15:00~18:00 会場:中会議室1,2
宗岡 徹(関西大学大学院会計研究科)
盛永 審一郎(富山大学大学院医学薬学研究部)
松井 陽(国立成育医療研究センター)
成田 昌稔(医薬品医療機器総合機構)
11) 医療機器におけるレギュラトリーサイエンス
15:00~18:00 会場:中会議室3,4
佐藤 智晶(東京大学政策ビジョン研究センター )
「社会科学系の立場から医療機器RSを考える(医療機器の定義、リスク・ベネフィットの考え方について)」
鄭 雄一(東京大学大学院 工学系研究科)
「評価の具体事例(長寿命型人工関節)」
鎮西 清行(産業技術総合研究所)
「直接作用型・間接作用型医療機器(医療機器評価の考え方について)」
村垣 善浩(東京女子医科大学)
「医療技術と医療機器(医療における医療機器の役割、リスク・ベネフィットについて)」
森永 修平(日本光電工業)
「評価の具体事例(植込型迷走神経刺激装置)」
三澤 裕(テルモ)
「販売後におけるレギュラトリーサイエンス(市販後調査、トレーニングについて)」
■ 一般演題(ポスター)
10:00~15:00 特別会議室101~103
なお、懇親会を9月2日18:15~、同じ会場で予定しています。